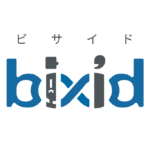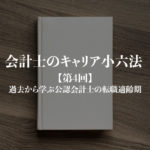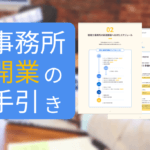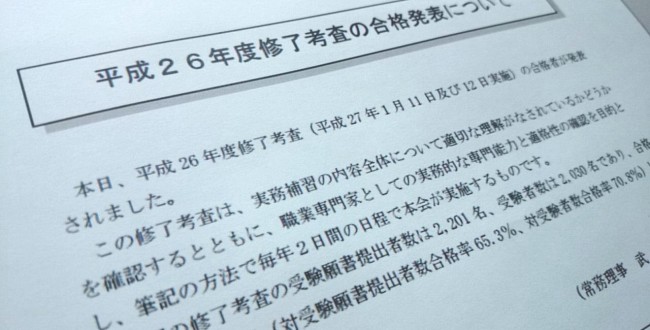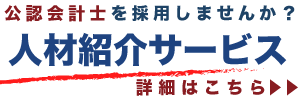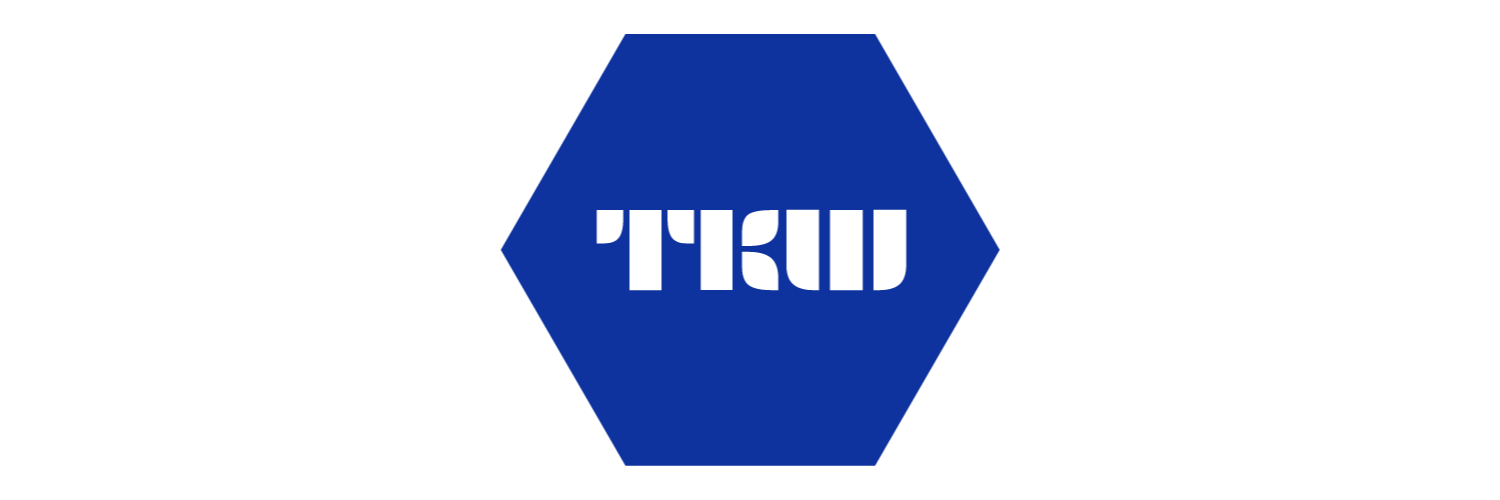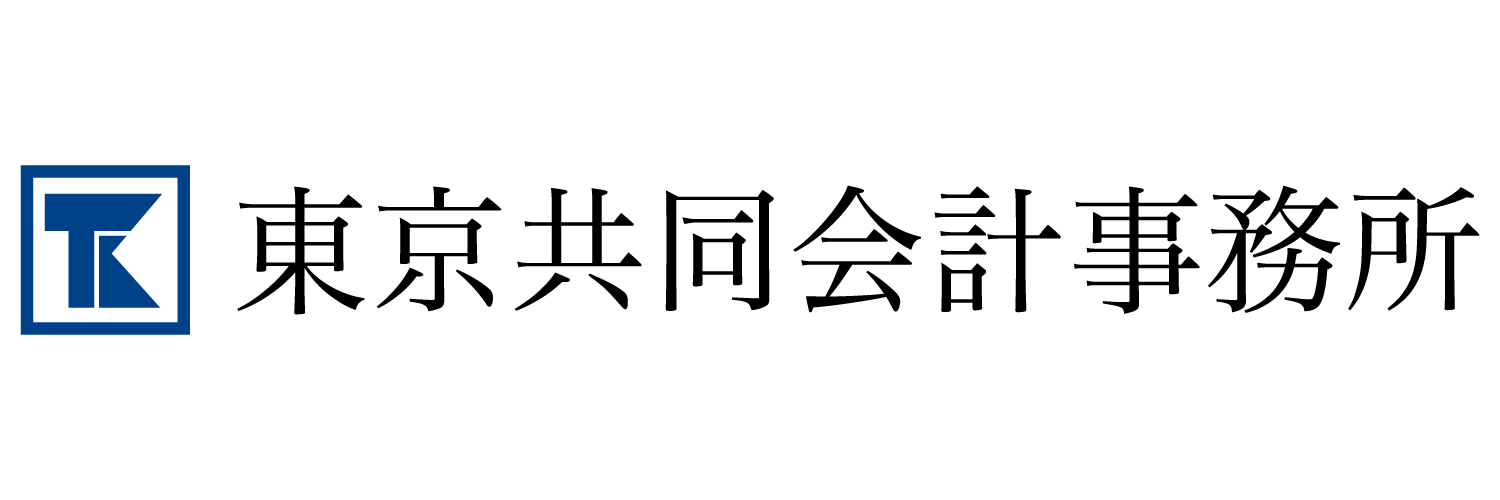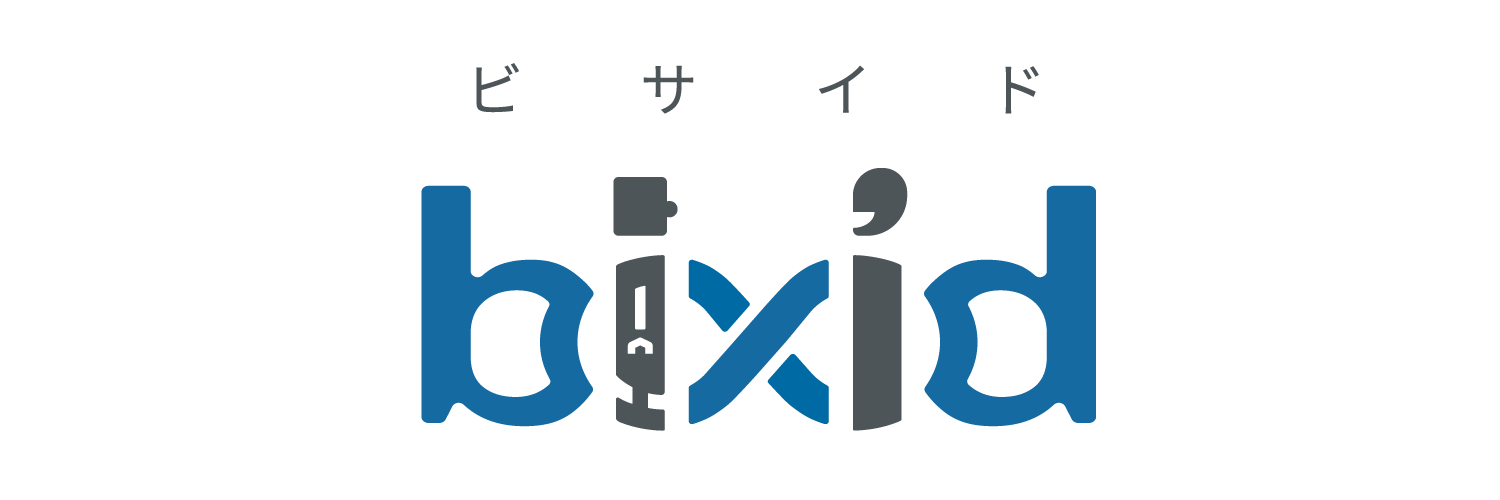公認会計士と弁護士というダブルライセンスをもつ菅沼 匠(すがぬま たくみ) 氏が代表を務めるリンクパートナーズ法律事務所(以下「リンクパートナーズ」)。菅沼氏と共にM&Aサービスを提供する弁護士・葛巻瑞貴氏もMBAを取得しているように、所属弁護士の多様なバックグラウンドを活かし、スタートアップや新興上場企業をはじめとした成長企業のM&Aを支えています。
両氏が「M&A支援に活きている」というバックグランドとは。それはどのように業務に活用されているのか。M&Aが増えるとマクロ的にもいいという理由は。菅沼氏と葛巻氏に話を聞きました。
本記事の目次
- スタートアップ・成長企業のM&Aを法務面から支援
- 法務だけでなく、ビジネス全体の視点を持ってM&Aを支援
- リンクパートナーズの強みは、弁護士たちの多様なバックグラウンド
- 経営者が「得意」に集中するためにも、M&Aは重要
スタートアップ・成長企業のM&Aを法務面から支援
── リンクパートナーズではどのような会社のM&A案件を手掛けているのか、教えてください。
葛巻:こちらの記事で言及したように、リンクパートナーズは多くのスタートアップ企業をクライアントにもつ法律事務所です。
その延長として上場・非上場を問わず「スタートアップを買収したい」または「大手企業に事業を売却したい」という相談を頻繁にいただいています。随時3〜4件の案件が動いていますね。
 葛巻 瑞貴(かつらまき みずき)
葛巻 瑞貴(かつらまき みずき)
リンクパートナーズ法律事務所
パートナー/弁護士、MBA
弁護士登録後、国際企業法務系の法律事務所において、専門訴訟実務、M&A(法務DDを含む)、国際商事取引、第三者委員会の調査業務等に従事する。弁護士業務の傍ら、経営学大学院へ入学し、経営戦略、組織論、マーケティング論、ゲーム理論、意思決定論、コーポレート・ガバナンス、コーポレート・ファイナンス等を学び、MBAを取得。
現在は、ファイナンス対応、IPO支援、M&A分野を専門としつつ、法学・経営学双方の知見を活かし、多数のクライアントの経営判断や意思決定に関するアドバイスを行っているほか、複数企業の社外役員を務め、コンプライアンスの向上に寄与している。M&A分野では、ディールの大小を問わず、幅広い支援実績を有している。
主な役職としては、地銀協コンプライアンス検定試験採点委員(一般社団法人全国地方銀行協会)、カード等相談センター相談員(第一東京弁護士会)。
菅沼:リンクパートナーズが扱った過去の案件でも、時価総額20億円~30億円だった会社がM&Aをきっかけに100億円規模にまで成長したり、300億円の会社が3,000億円になったりした例もあります。これは証券会社もM&A活用の好事例として紹介してくれているみたいです。嬉しいですね。
手前味噌ですが、大手法律事務所ならまだしも、中小規模の事務所で上場企業やスタートアップのM&A案件を、時にはスタートアップ業界で注目されるようなものまで、コンスタントに扱っているところは珍しいのではないでしょうか。
 菅沼 匠(すがぬま たくみ)
菅沼 匠(すがぬま たくみ)
リンクパートナーズ法律事務所
パートナー/弁護士、公認会計士
2001年、大学在学中に公認会計士試験に合格し、監査法人トーマツにて会計監査やIPO支援業務に従事。その後、ジャスダック証券取引所(現:日本取引所グループ)の上場審査部にて勤務。2005年にクックパッド株式会社に管理部第1号として入社し、株式公開、東証一部への市場変更などに関与する。その傍ら、司法試験を社会人合格。
2012年に弁護士登録し、2014年にリンクパートナーズ法律事務所を創業。上場支援、M&A支援の実績は多数。経済産業省による「我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項」の作成にも携わるなどスタートアップファイナンスの法務にも強い。
── 「スタートアップを買収したい」「大手企業への売却を検討している」といった相談はどういったルートで来るのでしょうか。
葛巻:ルートは様々です。既存の顧問先であるスタートアップからの相談、同じく既存の顧問先である成長企業が買収するケース、M&A仲介会社や証券会社から紹介されるケースなど、いろいろなルートからご相談をいただいています。ご紹介いただく場合は、これまでの実績を評価していただいたケースが多いですね。
法務だけでなく、ビジネス全体の視点を持ってM&Aを支援
── リンクパートナーズがM&A案件を扱う際の特徴はありますか?
菅沼:業種や企業規模を絞ったりはしていないのですが、我々としては成長している企業の支援をしたいなと強く思っています。
また、私は弁護士であると同時に公認会計士で、葛巻弁護士もMBAホルダーです。こういった経歴を活かし、法務だけでなく、ビジネス的な観点を大事にしています。
例えば、法務デューデリジェンスを始める前には、被買収企業の企業価値の源泉を必ず確認し、調査はそれから実施するようにしています。
当然、法務デューデリジェンスとして必要な手続きはすべて実施するものの、その確認こそが、期限も予算も限られている中でのM&Aを、より良いものとしてくれるんです。
── 企業価値の源泉をわざわざ確認せずとも法務デューデリジェンスはできるはずだけど、そのひと手間が重要ということですね。
菅沼:その通りです。このM&Aは、買収企業のビジネスにとってどのような位置づけなのか。それを確認してM&Aの道筋を考えないと、法務デューデリジェンスも明後日の方向に行きかねませんからね。
これがひいてはクライアントのためになると思って、重要視しています。

── 葛巻さんはMBAを取得しておられるのですね。
葛巻:はい。弁護士業と平行して取得しました。
私は前職で、国際企業法務系の事務所に所属していて、M&A関連では、医療機器や製薬会社の買収案件を担当していました。また、国際業務だけでなく、国内の保育園や高校受験予備校の事業の多角化に伴うM&A案件なども手掛けました。
リンクパートナーズに入所後は、スタートアップをはじめ、SaaS系ビジネス、合同会社や医療法人のM&Aにも携わっています。
── ご経験されている案件が幅広いですね。
葛巻:そうですね。M&Aをするにあたっては、業種によって論点が異なってくるんです。
例えば労働集約的なビジネスでは労務の重要性が高まりますし、装置産業では現場の情報が論点になることもあります。
過去に様々な業種と関わった経験が、リンクパートナーズでM&Aの法務デューデリジェンスを手掛ける上でも役立っていますね。
菅沼:私も公認会計士としてビジネスに携わってきましたし、事業会社の在籍中にその会社が上場したり、エンジェル投資をしたりもしてきました。
こういった経験もあってM&Aやスタートアップには詳しいと自負しています。経営者目線で法律面以外のアドバイスもできる点も、私や事務所の強みですね。
リンクパートナーズの強みは、弁護士たちの多様なバックグラウンド
── 多様なバックグラウンドが、法務だけでなくビジネス全体からクライアントを支えているんですね。
菅沼:その通りです。
私の場合、公認会計士・税理士としてのバックグラウンドを活かして、例えば、会計や税務の視点も含めたアドバイスを提供することもあります。「法務リスクだけで言うと買収ではなく事業譲渡でも良いですが、事業譲渡の場合は消費税がかかってトータルコストが上がってしまいますよ」といった具合です。法律事務所側としてのアドバイスなので、もちろん、会計事務所側のアドバイスを邪魔しない程度です。
葛巻:スタートアップをはじめ、小さな会社になればなるほど、基本的には組織の属人性は高くなります。そのため「キーマンクローズ*が大事な条件になりますよ」といったアドバイスをする機会も少なくありません。
必ずしも法務デューデリジェンスの範囲ではなくとも、普段からスタートアップと接している経験値を強みとして、M&A、ひいてはクライアントに接しています。
*M&Aの契約において、買収される企業の経営者やキーマンが、一定期間は会社に残って業務に従事するという条項。
菅沼:上場会社ならM&Aに慣れているケースもありますが、ほとんどの非上場会社はM&Aに慣れていません。そのため我々が指摘しなかったら最後まで気づかなかった論点があるということも珍しくないんです。こういった場合はリンクパートナーズの価値を特に発揮できていると感じます。

菅沼:M&Aは半分が失敗してしまうと言われています。ビジネス的な失敗だけなら仕方のない面もありますが、中には表明保証違反が判明するなど、法務的な問題が発生し、場合によっては訴訟に至るケースもないわけではありません。
私たちも実際、M&A関連の訴訟案件を扱ったこともあります。そういった経験の積み重ねが、お客様への予防法務のアドバイスとしても活かされていますね。
葛巻:繰り返しになりますが、リンクパートナーズには、公認会計士やMBAだけでなく、法学部以外の出身者や社会人経験を経てからの弁護士資格取得者など、多様な人材が集まっていて、これがクライアントのビジネスを見極める目を鍛えてくれています。
バックグラウンドの多様性が、クライアントとの二人三脚でのM&Aを支えてくれているんですね。
M&Aは足し算ではなくて掛け算になるのが理想。1+1を2ではなく、3にも4にもする。そうなったらそのM&Aは成功したと言えるでしょう。
法務だけでなく多角的にM&Aに関わり、そういう案件を生み出せるような支援をしていきたいですね。
菅沼:常日頃からクライアントと接してビジネスへの理解を高めておくことが、M&Aにおいて発生するであろう論点の事前予測に繋がります。
もちろんご紹介いただいてすぐにM&Aサービスを提供するケースもありますが、「はじめまして」の挨拶からいきなり法務デューデリジェンスに取り掛かっては、論点にも気づくのも遅くなりかねません。
そのため、M&Aをすると決まったら、なるべく早く声をかけていただけると嬉しいですね。
経営者が「得意」に集中するためにも、M&Aは重要
── 昨今、M&Aが話題となっているケースが多いように感じますが、マクロ的な動向はどう感じていますか?
葛巻:例えば2025年上期時点では、東証グロース市場の上場維持基準が論点となっています*。
それもあって、今後はグロース市場に上場した会社にとってもM&Aを用いた成長が重要なテーマとなるでしょう。スタートアップの数も増えていますし、注目度はますます上がっていくのではないでしょうか。*2025年上期時点では、グロース市場の上場維持基準を「上場してから10年後の時価総額が40億円以上」から「5年後の時価総額が100億円以上」に引き上げるかが議論されている。

菅沼:また経営者とディスカッションしていると、複数経営している企業の一部を売却したいと考えている方が少なくないのがわかります。そういった文脈でのM&Aも、今後は増えていく可能性があるでしょう。
例えば、0→1や1→10というステップは得意でも10→100は不得手という方は少なからずいます。一方で優秀な経営者ほど、0から立ち上げたいビジネスアイディアがどんどん湧いてくるはずです。
10まで成長させた会社を売却し、その資金を元手にさらなる起業にチャレンジする。そういった循環を整えるためにも、M&Aは増えてほしいですね。
葛巻:IPO支援をして無事に上場した後に、M&Aをしてさらなる成長を目指すケースも増えていくはず。そういった案件にも力を入れていきたいですね。
── 菅沼さん、葛巻さん、本日はありがとうございました。
取材・執筆:pilot boat 納富隼平