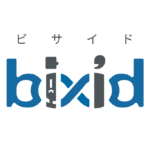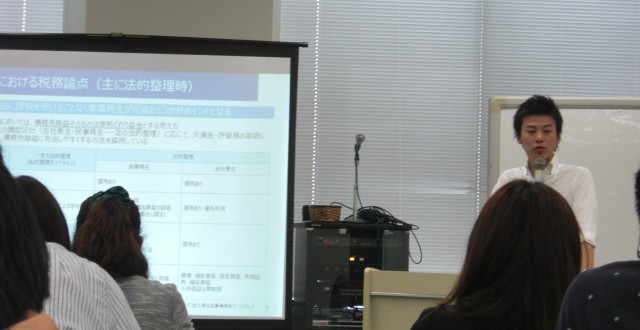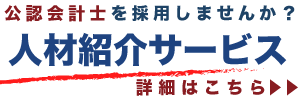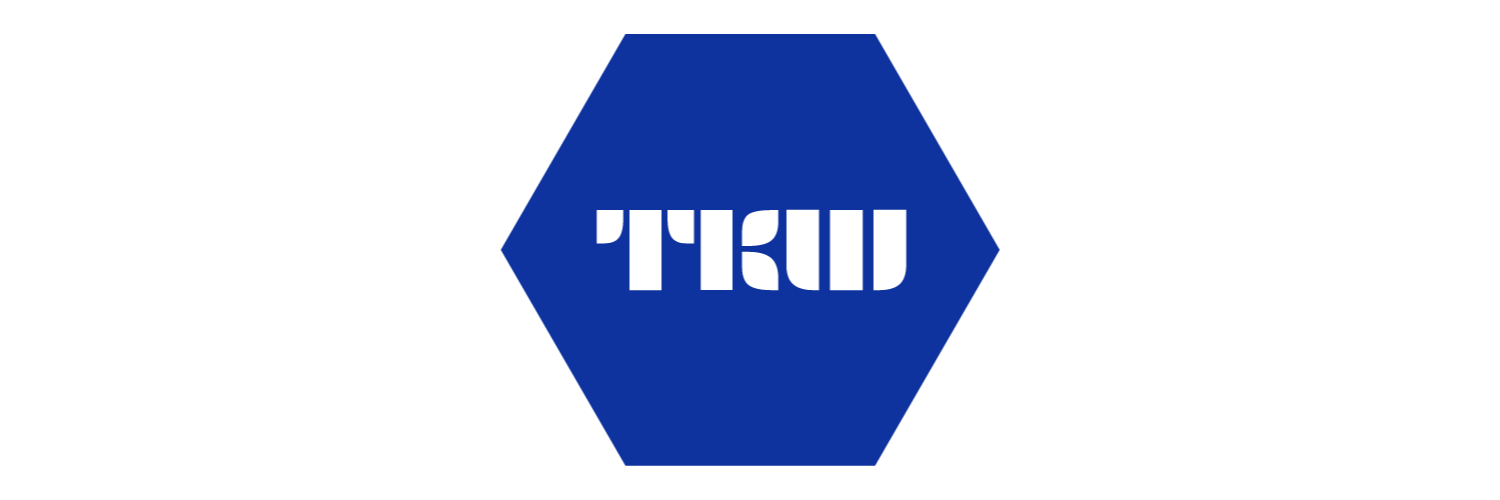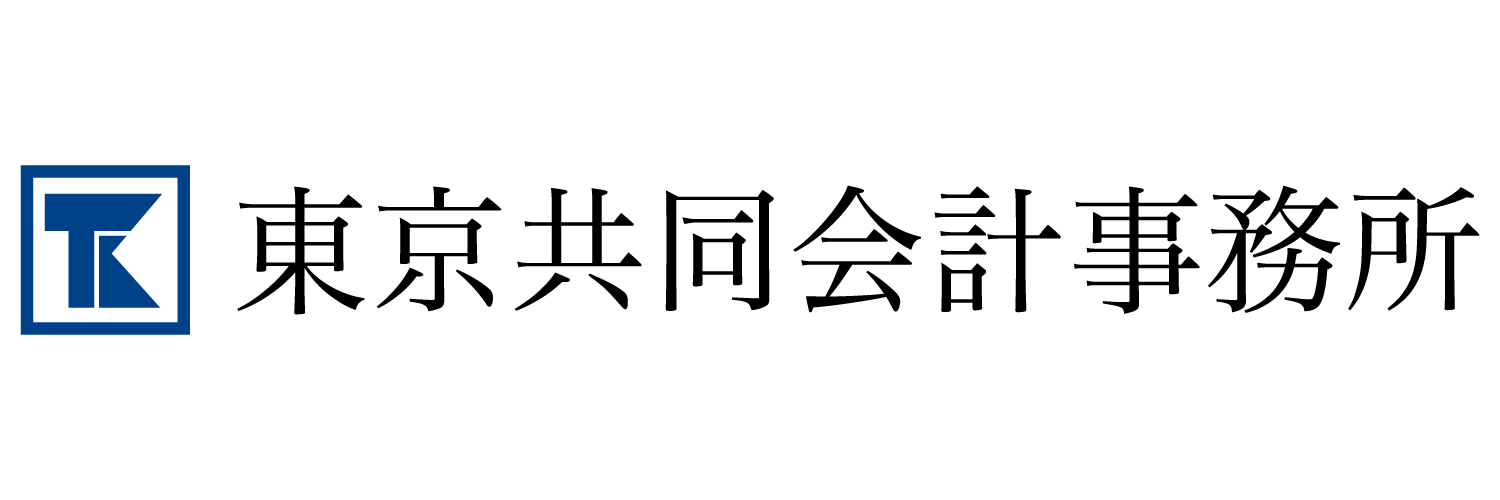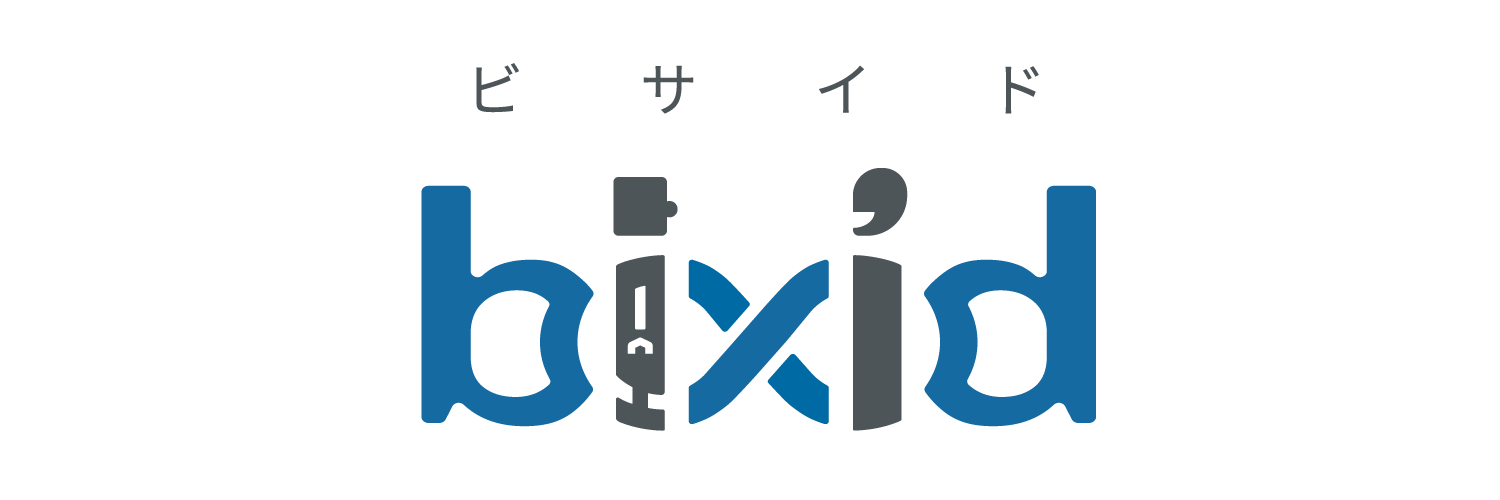2025年9月27日(土)に東京・茅場町にて第16回・公認会計士ナビonLive!!が開催されます。
本記事では、2025年3月29日に「会計士×付加価値との出会い」をテーマに開催された第15回公認会計士ナビonLive!!より、トークセッション「公認会計士×M&Aアドバイザリー:高度化するM&A市場で活躍するためのキャリアとは?」の様子をお届け。公認会計士ナビonLive!!の雰囲気を感じてみてください。
本セッションに登壇いただいたのは、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社(以下「DTFA」)の石川 佳代子さんと、グローウィン・パートナーズ株式会社(以下「GWP」)の小山 賢一さんのふたりの公認会計士。話題は、M&A業界での働き方、今と昔の違い、業界の魅力などに及びました。
モデレーターは公認会計士ナビ編集長の手塚佳彦が務めています。
本記事の目次
- 大手ファームと非大手ファームのM&Aアドバイザリーの違い
- 若手はどうM&Aスキルを磨くのか?それぞれのキャリアステップ
- M&Aの業界は忙しい? 実際のところは…!?
- ここが変わった。今と昔でM&Aはどう違う!?
- M&Aアドバイザリーの魅力は「二面性」、そのふたつの要素とは?
※本記事の登壇者の肩書・経歴等はイベント登壇時のものになります。
※本記事の内容は公認会計士ナビにてセッションでの発言内容に編集を加えたものとなります。
大手ファームと非大手ファームのM&Aアドバイザリーの違い
手塚(公認会計士ナビ):本セッションのテーマは「公認会計士×M&Aアドバイザリー:高度化するM&A市場で活躍するためのキャリアとは?」ということで、主題はM&Aアドバイザリーです。この業界は会計士にとって、監査に次ぐ主戦場と言っても過言ではないくらいのメジャーな領域となっています。
ただ、20年ほど公認会計士業界に関わっている私の立場から見ていると、M&Aとひと言にいっても昔よりも広く・深くなっている印象があります。
今日はBIG4と独立系それぞれのFAS系ファームのそれぞれの立場から、M&Aの話を聞かせてください。
石川(DTFA):DTFAの石川佳代子でございます。
私は元々、東京大学大学院の博士課程に在籍していました。ただ当時は就職氷河期で研究環境が悪化していたこともあり、思い切って方向転換。公認会計士の資格を取得して有限責任監査法人トーマツに入社した1年後にDTFAに転籍しました。現在はM&Aにおける財務デューデリジェンスや事業再編、事業売却に係るアドバイザリーなどを担当しています。
 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
M&Aトランザクションサービス
マネジャー/公認会計士
石川 佳代子
東京大学文学部卒業、同大学院博士課程中退。学者を目指していたが、不況による研究環境の悪化を感じて方向転換を行い、2005年公認会計士試験に合格。同年12月に有限責任監査法人トーマツに入社し、監査部門にて化学、通信、製造業を中心に会計・内部統制監査業務やIPO業務に従事。
2009年12月よりデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に転籍。M&Aにおける財務デューデリジェンス業務や企業価値評価、事業再編や売却に係るアドバイザリー業務等の多様な業務を幅広く手掛けている。
石川(DTFA):DTFAはM&Aのプレディールからオンディール、ポストディールまで、一気通貫でアドバイザリー業務を提供しているファームです。各メンバーが専門とするサービスラインと専門インダストリー/セクターをかけ合わせたマトリクス組織を採用している点が組織上の特徴となっています。
私は現在、財務デューデリジェンスサービスを提供するトランザクション部門に所属しながら、セクターとしてはエネルギーとケミカルを担当しています。
小山(GWP):GWPの小山です。海外フィナンシャルアドバイザリー部(現フィナンシャルアドバイザリー2部)でヴァイスプレジデント、いわゆるマネージャーをしています。
2010年に会計士試験に合格して、EY新日本監査法人で6年弱監査を経験。その後、当社に入社しています。
 グローウィン・パートナーズ株式会社
グローウィン・パートナーズ株式会社
海外フィナンシャルアドバイザリー部(現フィナンシャルアドバイザリー2部)
ヴァイスプレジデント/公認会計士
小山 賢一
2010年、公認会計士試験合格。新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)にて、総合電機メーカー、自動車部品メーカーに対する会計監査業務、内部統制監査業務、IFRS導入支援業務に従事。
グローウィン・パートナーズ株式会社に入社後は、主に国内外の財務デューデリジェンス業務、バリュエーション業務に従事。トランザクションサービスを中心に、国内・海外M&Aや事業承継など多数の案件に関与し、現在は海外フィナンシャルアドバイザリー部にて国内・海外M&A案件、海外拠点再編や経理財務のコンサルティングを中心に担当。
小山(GWP ):私は現在、財務デューデリジェンスやバリュエーションを中心とした、国内外の案件を担当しています。最近はGWP の親会社であるタナベコンサルティンググループ経由で、中堅・中小企業の財務コンサルティングにも携わっています。
手塚(公認会計士ナビ):おふたりに自己紹介していただきましたが、同じM&A業界ということで今お話いただいたサービスは似ているように聞こえるものの、ご両社の実態はかなり異なるかと思います。その点を掘り下げさせてください。
まずクライアントのディールサイズはどれくらいでしょう?
石川(DTFA):皆さんのご想像の通り、DTFAが扱う案件のサイズは非常に大きいものが多くなっています。
小山(GWP ):小さいと数億円、大きくても数十億円です。百億円にまでなると会社としてはかなり大きなディールです。GWPのクライアント層は、いわゆる「ミッド・スモールキャップ」と呼ばれるサイズが中心です。
手塚(公認会計士ナビ):DTFAさんはインダストリー/セクターと、サービスラインごとでチームが分かれているという話でした。私が知る限り、BIG4のFASの中でインダストリー/セクター別で明確に組織を分けているのはDTFAさんくらいかなと思います。どのくらいの数に分けているのでしょうか?
石川(DTFA):インダストリー/セクターは10部門ほどに分かれています。私はエネルギーとケミカル業界を担当していますが、これらはかなり特殊な会計処理等が必要とされる業界です。専属となることで知見が貯まって次の提案にも活きていますね。
サービスラインについては、公認会計士はこれまで財務デューデリジェンスを中心に携わる方が多かったように思います。
ただ最近は皆さんの関心が広がっているようで、CFA(投資銀行業務)やバリュエーションの道を選ぶ方も増えてきました。

手塚(公認会計士ナビ):GWP さんはセクター分けはしているんですか?
小山(GWP ):セクターでは分けられてはいません。
M&Aアドバイザリー部門は、「買い手が上場企業で売り手が未上場企業」「中小企業同士」「未上場会社同士」といった『国内M&A』と、In-Out(国内企業による海外企業の買収)の『クロスボーダーM&A』の大きくふたつで分けられています。
手塚(公認会計士ナビ):サービスラインベースで、セクターは問わず対応しているんですね。
小山(GWP ):はい。サービスラインにしても昔は財務デューデリジェンス、バリュエーションの業務が多かったのですが、ブティック系ファーム出身者や仲介会社出身者など新たなスキルを持った方が入社するなど、会社の成長に合わせて、次第に国内外のFA業務や仲介業務も増え、現在のラインナップへと拡大してきました。
若手はどうM&Aスキルを磨くのか?それぞれのキャリアステップ
手塚(公認会計士ナビ):小山さんから「サービスの範囲を拡大してきた」という話がありました。
公認会計士が運営しているM&Aファームに関しても、昔は財務デューデリジェンスメインだったのが、近年ではPPA(無形資産価値評価)、PMI(M&A後の統合プロセス)などに対応する会社も次第に増えている印象があります。
 株式会社ワイズアライアンス
株式会社ワイズアライアンス
代表取締役CEO/公認会計士ナビ 編集長
手塚 佳彦
手塚(公認会計士ナビ):DTFAさんはサービスラインごとに部門が分かれているとのことですが、ひとつのディール内での部門間の業務受け渡しや引き継ぎはどのように対応されているんでしょうか?
石川(DTFA):一般的には、M&Aを行うクライアント企業は、例えばバリュエーションはあるブティックファームに、デューデリジェンスはBIG4系ファームに、FAは投資銀行に…と、サービスラインごとにバラバラに依頼するケースも少なくありません。
一方DTFAでは、社内だけでなるべくサービスを完結させるようにしています。例えば、CFA、バリュエーション、財務デューデリジェンス、タックス、ITデューデリジェンス、PPAといったチームが一体となって大チームを組成して案件に対応する、といった具合ですね。
手塚(公認会計士ナビ):昔からこの仕組みを採用しているのでしょうか。
石川(DTFA):いいえ。今でこそDTFAはBIG4の中でも大きなファームとなりましたが、私が入社した当時は250人程度の小さな所帯だったんです。私もバリュエーションやCFA、ビジネスデューデリジェンスと、とにかく何でも対応していました。
その後人数が増えてきた段階でサービスラインの増設を行い、その後に業界知識を培うためにインダストリー別の要素も加えたんです。そうして今の仕組みとなりました。
手塚(公認会計士ナビ):なるほど。インダストリーに紐づいた組織の中で、サービスラインごとの組織が案件ごとにチームを組んで連携していくわけですね。
GWP さんは逆に幅広くやっているかと思いますが、とはいえ、入社していきなり何でもできるわけではありませんよね。若手が入社するとどういった業務を担当して、昇進と共にどのように変化するのか、教えてください。
小山(GWP ):GWP ではM&Aの基本はバリュエーションであると考えています。そのため、最初はトレーニングでファイナンスの基礎知識を修得し、バリュエーションの実務に臨みます。
アナリストやコンサルタントの間はバリュエーションを基礎としつつ、本人の希望も考慮の上、FA、財務DD、仲介など幅広に経験の機会を設けるようにしています。
その後、シニアコンサルタント以上になると、「国内案件のFA業務の経験を更に磨きたい」「会計や財務分析に興味があるから財務デューデリジェンスにより注力する」「国際業務に関心があるから海外案件に取り組んでみる」といった形で、それぞれの関心に合わせて業務を選んでいく、というキャリアパスのパターンが多いです。
手塚(公認会計士ナビ):DTFAさんも似たような仕組みですか?
石川(DTFA):そうですね。ファイナンス系の研修は必須です。新入社員はその上で、入社時に第2希望までサービスラインを選べるようになっています。

M&Aの業界は忙しい? 実際のところは…!?
手塚(公認会計士ナビ):働き方についても聞かせてください。一般的には「M&A業界は忙しい」と言われているかと思います。実際のところはどうなのでしょうか。
石川(DTFA):ディールの種類によって変わってきます。
バイサイドなら1〜1.5ヶ月ほどの短期決戦で頑張ってもらうケースが多く、その期間が忙しいのは間違いありません。
一方、セルサイドのカーブアウト案件では、長いと3年、通常でも1年ほどクライアントに伴走することになります。それだけ長い期間をかけていると多少時間が空くこともあって、その間に休暇を入れるケースが多いですね。
手塚(公認会計士ナビ):監査のようにまとめて長期休暇を取るのではなく、プロジェクトの合間にある程度まとまった休みをポンポンと入れるようなイメージですね。
日々の労働時間はどれくらいですか?
小山(GWP ):平時は長くても10時間/日程度です。私は子育てをしながら働いているため18時頃に一旦仕事を切り上げて、家庭の時間を優先しています。急ぎの仕事がある場合などは子供が寝てから1~2時間程仕事をすることが多いです。柔軟に働くことができているため、仕事と家庭の両立は実現できています。
特に忙しくなるのは、例えば入札のM&A案件を担当する場合です。プロセスや期限が厳密に決まっているので、それに間に合わせなくてはなりません。この期間は正直、遅くまで働くこともあります。出来る限り日を跨がないように、段取りやto doの優先順位をチームメンバー内で摺合せます。
石川(DTFA):手塚さんの言う通り「M&Aの業界は多忙」だと耳にする機会も多いかと思います。しかしここ3年ほど、働き方改革やDEIが重視されるようになってきて、BIG4も状況が変わってきました。
DTFAでは、スタッフ・シニアスタッフは、どんなに遅くても平時は22時までには仕事を終わらせてもらうようになっていますし、申請された休日は100%近く承認が降ります。
もちろん業務の状況によっては1〜2日ほど頑張ってもらう場合があるのは否めませんが、それは監査も同じですよね。監査を経験されていれば、M&A業界にも問題なく耐えられるかと思います。

手塚(公認会計士ナビ):ファームとしては当然、売上・利益を上げていきたいけれども、人手不足という状況の会社も多いと聞いています。スタッフに頑張ってもらって売上げを取りにいくか、スタッフに無理はさせないのか、ファームの考え方が出そうですね。
小山(GWP ):GWP はブティックファームなので、人のリソースには限界があります。そのため必要なときは独立している会計士と連携することも少なくありません。
手塚(公認会計士ナビ):ではM&A経験のある会計士の方が独立したら、まずはGWP さんに挨拶に行かれるのが良いかもしれないですね(笑)。
小山(GWP ):お待ちしています(笑)。
手塚(公認会計士ナビ):M&A業界は特に会計士の方々を採用したいと考えておられますから、M&A業務にチャレンジしたい会計士の方が増えて欲しいですね。
石川(DTFA):おっしゃるとおり「人は力」の業界です。会場にいらっしゃる方には、ぜひM&A業界にいらしていただきたいです(笑)。
ここが変わった。今と昔でM&Aはどう違う!?
手塚(公認会計士ナビ):石川さんから、近年はM&A業界も働き方が変わってきているというお話がありました。最初に頭出したように、私もこの十数年で変化が生じているように感じます。他にも、M&Aについて変化はありますか?
小山(GWP ):近年、上場企業の資本コスト意識が徹底されたり、東証がグロース市場の上場維持基準の見直しなどの動きの中で、M&Aを活用した企業規模の拡大や企業間の合従連衡が促進されています。
また、中小企業向けのM&Aにおいても、品質向上が求められるようになってきました。このように現在のM&A市場は大きな変化の波が訪れています。
こうした動きにはファームとしても対応しなければなりません。GWP では例えば、社員が蓄積してきた経験や知識を体系化し、ガイドブックやチェックリストとして整備することで、組織全体のナレッジを共有・活用できる仕組みを構築しています。
石川(DTFA):昔と比べて、クライアント企業がM&Aに慣れているケースが増えていますね。
ひと昔前はM&Aというと「社運を賭けたプロジェクトではあるものの、何をすればいいかわからない」という会社は珍しくありませんでした。しかし今は、「企業の成長のためにはM&Aが不可欠だし、不採算事業のカーブアウトも必要だ」と誰しもが認識しています。
そのため、クライアント企業にM&A業務の経験がある方がいらっしゃるケースも出てくるようになってきました。ファンドで活躍した方が社内にいるような場合は、我々にも高度な依頼が来るようになっていますね。

手塚(公認会計士ナビ):上場会社による買収の場合には、監査法人の意見も重要になるケースが多いと思います。監査経験が活きる場面もあるのではないでしょうか。
小山(GWP ):のれんを含め見積りの要素は、監査法人時代のノウハウが活きています。上場会社の経理部にも重宝いただいていますね。会計士×M&Aは、そういった点がやはり強みになるのかと思います。
石川(DTFA):特にのれんの論点は必ず監査法人とクライアントが協議をして、調整していただくようにしています。その際に監査経験が活きることは多いですね。
M&Aアドバイザリーの魅力は「二面性」、そのふたつの要素とは?
手塚(公認会計士ナビ):ここまで話を聞いて、おふたりはM&Aの業務を楽しんでいるように見えましたが、いかがですか?
石川(DTFA):私自身は非常に楽しんで仕事をしています。
監査では特定の時期に仕事が発生しますよね。それに対してM&Aは1.5〜2ヶ月おきに、次から次へと案件がやってくる。短期間かつ限られた情報の中で、企業の本質的な収益や事業の状況を理解しなくてはならないという状況には、謎解きをするような面白さを感じています。監査とは別の楽しさですね。
また、M&Aには複数の利害関係者が絡み合ってきます。あるべき方向に向けて、あちこちを説得して調整をしていくという作業は、非常に人間的です。もちろん専門的な会計知識も必要なのは説明するまでもありません。「人間的な局面での勝負」と「専門性」。この二面性がM&A業界の魅力です。
小山(GWP ):近年TOBや、中小企業の事業承継案件が増加しており、これからM&A業界はさらに活発化していくと予想されます。このような環境の中で私自身もスキルや知識を磨き、取り組める領域を広げていくことで、より楽しめるような気がしています。

手塚(公認会計士ナビ):最後に、小山さんと石川さんが今後のキャリアについて考えていることや、M&Aアドバイザリーというキャリアに興味がある方へのアドバイスをください。
小山(GWP ):私はこの先1〜2年程は「勝ちが確定している仕事」ばかりをしないようにしようと考えています。自分にとって難易度の高い業務や、これまで経験のない領域に積極的に挑戦していきたいと考えています。
例えば、海外企業を買収した後のPMI業務は難易度が高く、「勝ちが確定している」とは言い難いので、挑戦していきたいです。新しい仕事をどんどん見つけてきて、会社としても個人としてもケイパビリティを上げていきたいと考えています。
石川(DTFA):私はこれまで、バリュエーションに始まり、CFAやビジネスデューデリジェンスなど、偶然とはいえ幅広い業務を経験してきました。これが今、マネージャーの立場になって役立っていると実感しています。
皆さんも「会計士だから財務デューデリジェンスだけ」と考えるのではなく、色々な業務に取り組んでいただきたいです。それがいずれ、様々な利害対立を解決する一助になっていきます。自分の得意分野以外の話が来ても、臆せずチャレンジしてみるのがいいと思いますし、私もそれを心がけています。
手塚(公認会計士ナビ):本日は「公認会計士×M&Aアドバイザリー」をテーマに、M&Aのキャリアについて聞いてきました。石川さん、小山さん、ありがとうございました!

【参加受付中!】第16回 公認会計士ナビonLive!! 開催!
第16回・公認会計士ナビonLive!!の開催が決定!
「公認会計士と専門スキルの選び方」をテーマに、「独立」「会計コンサルティング」「会計×テクノロジー」「PEファンドからの独立」といった分野にフォーカスをして公認会計士の方々にお話を伺い、みなさんとの交流の機会をお届けする予定です。みなさまのご参加お待ちしております!