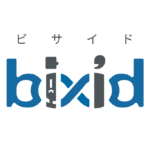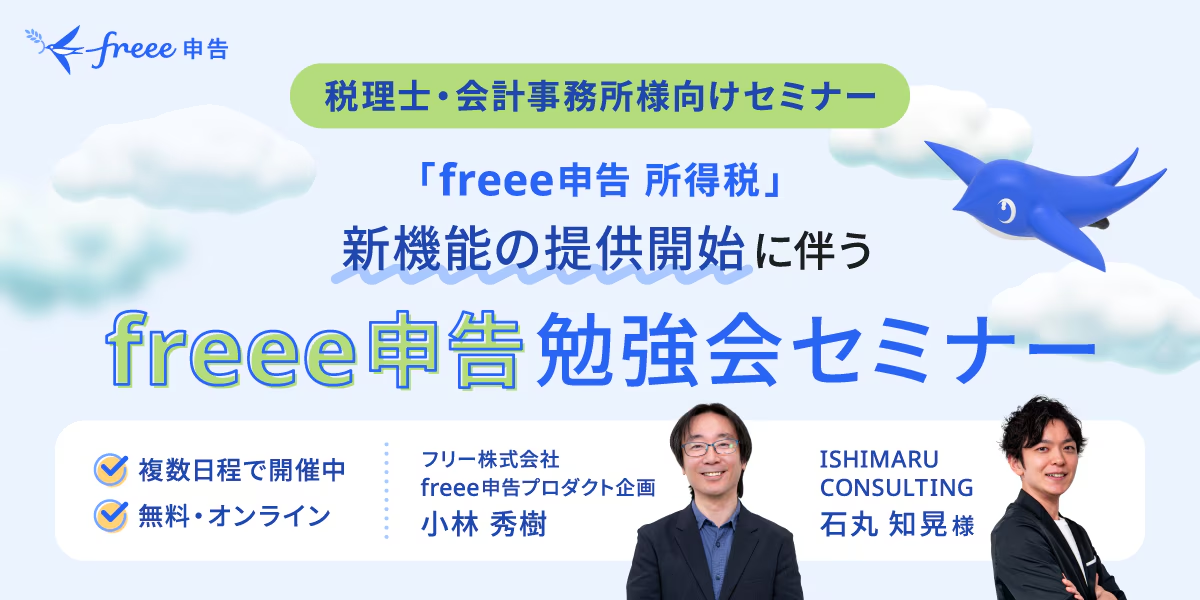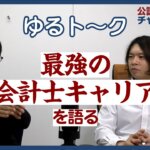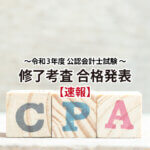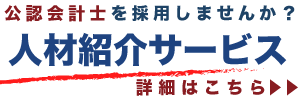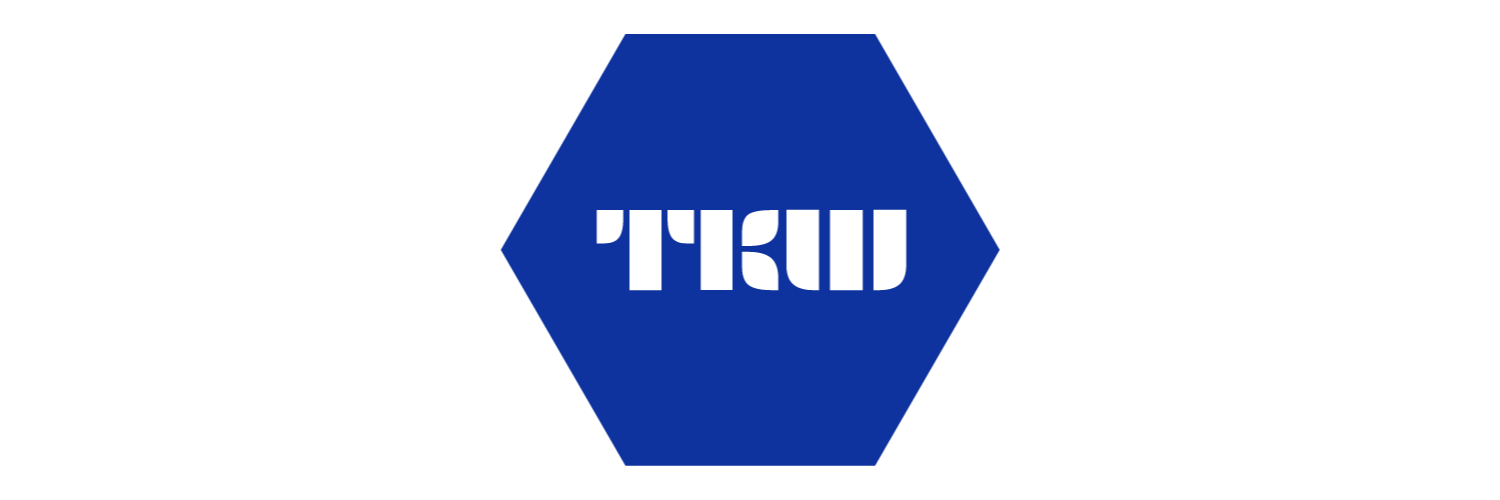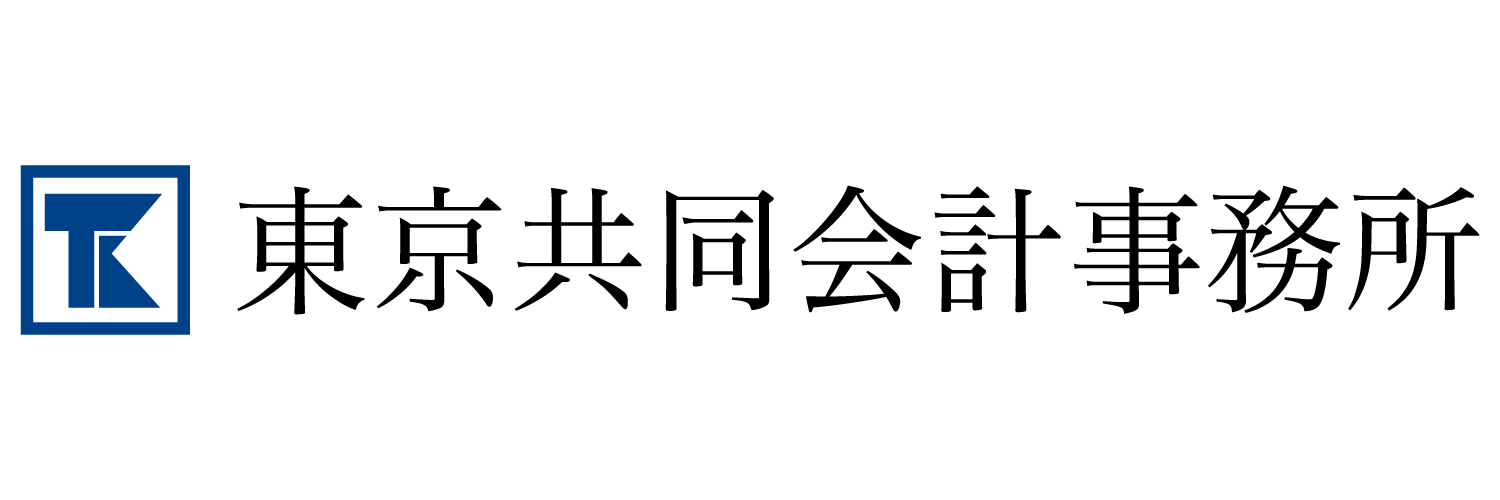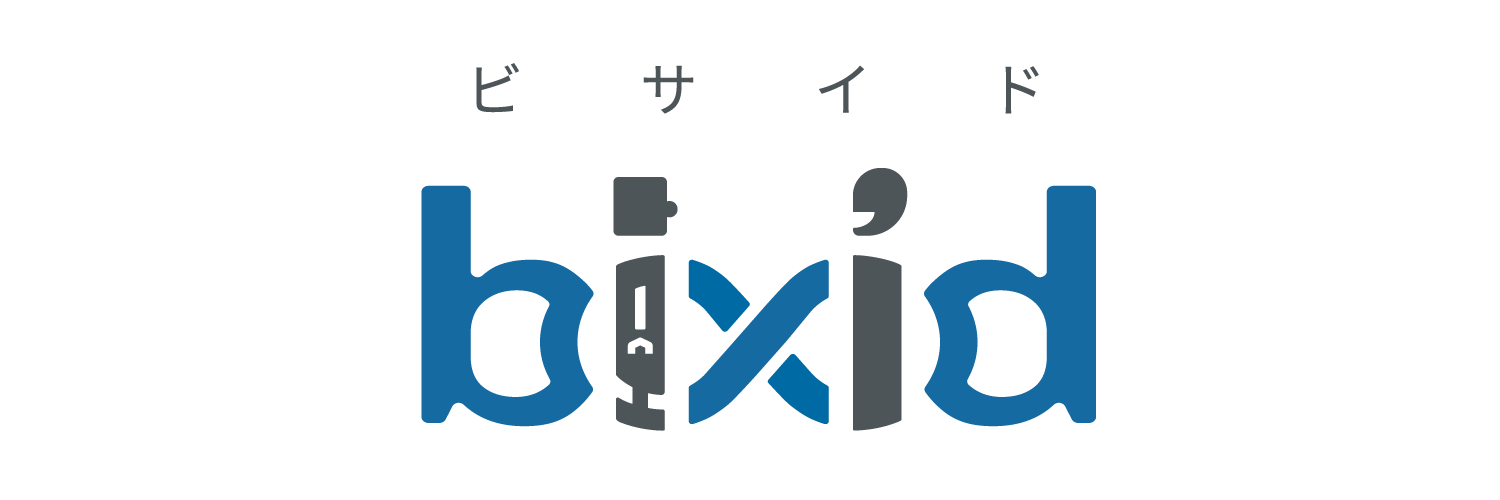「実家が税理士事務所を経営していて、自分もいつかは継ぐつもり。でもせっかくだから税理士じゃなくて公認会計士にしようかな。」
公認会計士には、そんな理由で資格を目指した方も多いのではないでしょうか。これから独立開業を目指す会計士にとっては、既にある強固な地盤を引き継ぐのは羨ましいかもしれません。
でも、二代目、三代目にも苦労はあるんです。
今回訪ねたのは、東京のBIG4監査法人で地方銀行の会計監査を経験した後に、独立系ファームで再生案件を学び、神戸の家業の税理士事務所・税理士法人希水会に入所した河北啓二さん。
河北さんに二代目として気を付けていること、東京と神戸・会計士と税理士の違い、税理士として大切な人脈の築き方について伺いました。
鍵は「コミュニケーション」と「自分の価値の出し方」です。
 税理士法人希水会 河北事務所
税理士法人希水会 河北事務所
公認会計士 / 税理士
河北啓二
2015年、公認会計士試験合格。EY新日本有限責任監査法人 金融部にて地方銀行を中心とした監査や内部統制監査業務に従事後、J-TAPグループにて主に中小企業の経営改善計画作成業務に従事。
兵庫県神戸市出身、早稲田大学商学部卒。
家業に活かすために、地銀の監査を志望
── まずは河北さんが家業を継ぐまでの話を聞かせてください。公認会計士を目指したのはいつのことでしょうか。
大学4年生の頃です。周りが就職活動を始める中、自分は勉強することを選びました。商学部だったので多少は簿記の勉強はしていたものの、それまで特に資格試験のための勉強をしていたわけではありません。
── 家業の税理士事務所を継ぐために先んじて勉強していたわけではないのですね。ところで、なぜ税理士ではなく会計士を選んだのでしょうか。
浪人して大学に入ったこともあって、3年間は遊んでしまいました(笑)。そこから心機一転、勉強を始めています。
私は早稲田大学商学部に在籍していたのですが、学部やゼミのメンバーには会計士志望が多かったので、周りに流されたという面はあります。
また、私には兄がおり、彼は当時、税理士を目指していたんです。父親からは「じゃあ、おまえは会計士にしたら?」と言われ、会計士を選びました。
ちなみに、兄は希水会のもう一方の事務所で税理士をしています。
── 試験に受かったのは27歳のときですね。
大学卒業後、5年かけて合格しています。周囲と比べると遅いほうですね。合格後はEY新日本有限責任監査法人に入社し金融事業部に配属されたのですが、同期60人のうち半数が現役学生だったため、余計に自分の年齢を感じました(笑)。
── なぜEY新日本を選んだのでしょうか。
私は論文式試験に一度落ち、就職活動を2回行っています。その中で多くのリクルーターの方と出会いお話をするなかで、将来を考えると地銀の監査がやりたいと思うようになりました。
EY新日本は地銀のシェアが高く、それが決め手でした。大学の学部の友達が私より3年ほど先に入社していて、ちょうどEYでリクルーターをしていた縁もありましたね。
── なぜ地方銀行の監査を希望したのですか?
いずれは実家に戻るつもりだったので、中小企業に関係する仕事がしたいと考えていました。それで自己査定がある地銀の監査が役立つと思ったんです。就職活動中に出会ったリクルーターが地銀担当だったこともあって、希望通りの部署へ配属が決定。もし地銀監査でなければ金融部にこだわる必要はなかったので、配属先が決まったときは安心しました。
── EY新日本にはどのくらい在籍していましたか?
修了考査に合格した時期までいたので、3年半程です。後悔しているわけではありませんが、監査の面白みがよくわからないまま辞めてしまったという思いがないわけではありません。
ただ、いつかは実家に帰ろうと思っている中、監査以外の業務の経験をするためには残された時間が少なかったので転職を決意しました。
その後は知り合いから紹介してもらい、J-TAPグループ(以下、J-TAP)という会計ファームに転職しています。
修行のために手掛けた事業再生案件の大変さ
── すぐ家業に戻ったわけではないんですね。
はい。その前に修行をしたいと考えたんです。とはいえ一般的な税務業務を学ぶなら、さっさと実家に帰ればいいだけ。それで事業再生を手掛けているJ-TAPに転職しました。

── J-TAPではどのような仕事をしていたのでしょうか。
当時のJ-TAPは、これから拡大しようというところでしたので、非常勤の方を除けば、公認会計士は私と代表の片寄学さんだけ。片寄さんはとても頭の切れる優秀な方で、マンツーマンでたくさんのことを教えてもらいました。
私の能力が低かったこともありますが、業務以前の論理的思考能力や文章能力について徹底的に指導されました。就職してからこれらの能力にひとつひとつ指導してくれる上司はいないと思うので、そういった意味でも感謝しています。初めて監査以外のことにチャレンジしたこともあり、当時はしんどかったですが(笑)。
片寄さんに厳しく指導していただきながら、405事業と呼ばれる経営改善計画作成をメインとした事業再生案件に携わりました。クライアントの経営改善計画を半年ほどかけて作成し、銀行と合意をしたら、助成金・補助金が出るというものです。その後の継続的なモニタリングも実施しました。
── 順調に経験を重ねていったんですね。
もちろん大変なこともありました。中小企業の皆さんをサポートするのはやりがいのある仕事でしたが、再生案件の対象となる会社は赤字企業で、資金繰りが厳しく、かといってすぐに売上が増えるわけでもありません。明るい話がなく、社長には元気がない。社長の家庭背景なども知っているし、並走するのは精神的に、想像以上に厳しかったです。実際に業務に入ってから、その大変さに気づきました。
また入社して1年もしないうちに、コロナ禍に陥り、仕事もリモートワークになってしまったんです。それまでずっと机を向き合わせて片寄さんとコミュニケーションを取りながら何とか仕事をしてきたのですが、オンラインだと細かな意思疎通が難しくなってしまいました。
案件が佳境のときには当然ハードワークをしなければなりませんが、在宅でずっと働くというのも私は辛かったです。
── そのタイミングで実家に戻る話があったのですね。
はい。子供がちょうど幼稚園に入るタイミングで、実家の事務所からも「そろそろ帰ってきてほしい」という話がありました。いろんなタイミングも重なり、2022年の春に神戸に戻り、税理士法人希水会河北事務所に入所しています。
出戻り二代目として気を配るべきこと
── 希水会河北事務所ではどういった業務を担当しているのでしょうか。
95%は中小零細企業の税務業務です。税務は初めてなので、ベテラン職員の方や父である所長に一から教えてもらっています。
── お父さんが上司ということで、仕事にやりにくさはないですか?
父は頭ごなしに否定するようなことはなく、いったん私の意見を聞いてくれるので、やりにくさを感じる場面はほとんどありません。
逆に、私は私で、所内では所長と呼んだり、父を立てるようにしています。
今はその関係性が上手くいっていますね。

でも、仮に私が税理士試験に受かって税理士として経験を積んで帰ってきていたら、もしかしたら喧嘩が起きていたかもしれないなと思うことはあります。
実際には私は税務未経験の公認会計士であり、経験豊富な税理士である所長の言うことは素直に聞くしかないので、それが上手くいっていますね。
業務はもちろんゼロから覚えないといけないので、特に1年目は大変でしたが、そこはもう慣れの問題だと思います。
また私の場合は、ベテラン職員の方も昔から面識があって、歓迎してくれました。事務所の人間関係で苦労がなかったことは、僕にとって幸運でしたね。
── 家族だけでなく、職員さんとの関係性も大事ですね。
そうですね。二代目が継ぐ際、東京から会計士資格をもった息子が偉そうに戻ってきたら、職員の方々が嫌な顔をして当然です。面識があったとはいえ、私も気を付けました。「何もわからないので教えてください」という感じですね。
また、もしかしたら会計士自身は認識していないかもしれませんが、会計士の世界は横文字が多いんです。そういった専門用語はできるだけ使わないようにしました。地味なことですが、大切なことだと思います。
── 会計士と税理士では文化が違うものですか?
全然違いますね。会計士は相手が上場企業のクライアントですし、監査法人内も、アシスタントを除けば全員が公認会計士。共通言語や背景が一緒だから、話が大体通じるんです。
一方で税理士事務所には色んな背景の方がいて、それはお客様も同様です。人や場面に応じた対応が必要で、今でもその点には気を配っています。
── プライベートでも仕事の話はするのでしょうか。
我が家ではしますね。私はあまり公私をしっかり分けたいタイプではないですし、父も気にしていないと思います。所内に所長と2人しかいなければプライベートの話もしますし、逆に家族とご飯を食べている際に仕事の話が出てくることもあります。
母にしても、父が開業した時から家で仕事の話もしていたので、なんとも思っていないはずです。

希水会河北事務所は河北啓二氏、河北氏の父である裕二氏と、土田徹氏(写真右)の税理士3名体制。土田氏は河北啓二氏の会計士予備校・監査法人の同期で「家業に戻ったら一緒に働こう」とずっと口説いていたそう。
地元で人脈を築く術
── 希水会河北事務所は神戸を拠点としています。東京とのギャップは感じますか?
地域柄はありますね。お客様との距離感が全然違います。関西の方が社長ともフランクに話しますし、1回信頼してもらえたら何でも話してもらえるというイメージです。
── 東京から戻って大変なことはありますか?
税理士事務所を営む上では、人脈は非常に重要です。
しかし私は大学も監査法人も東京だったので、地元の人脈は一から築くしかありませんでした。実家に戻ったら早く自分の売上を作りたいと思うものですが、この状態ではそれが厳しかったのは事実です。
私は元々の事務所の基盤があるから生活に困ることはありませんでしたが、ゼロから独立となったら、その前に人脈を築く期間を設けた方がいいかもしれません。
そういう意味では、最初のキャリアや転職先を大阪や神戸の監査法人にしても良かったかもしれません。とはいえ東京でしかできない経験もあったので、難しいところですね。
── 地元で顔を広げるための活動はしていますか?
神戸の商工会議所の士業の集まりに顔を出しています。新規の仕事はここからいただくものも多いですね。社労士や司法書士、行政書士の方からご紹介いただきます。参加してから1年ほどは紹介がほとんどなかったので、人脈づくりには1年ぐらいかかると考えておくとよいのではないでしょうか。
── 他士業の方が、新たに税理士を探している会社を紹介してくれるんですか?
新規設立のお客様をご紹介いただけることもありますし、既に税理士はいるけどコミュニケーションが上手く取れずに不満があったり、税理士が引退を考えていて、後任を探していたりするケースもあります。いずれにせよ、すでに他士業の方が関係性を築いているお客様をご紹介いただくので、お客様との話もスムーズにいくことが多いです。
ちなみに、他士業にはこちらからも仕事を依頼することが多いので、信頼できる仲間ができると業務上すごく助かります。
── 最後に、将来家業を継ぐ予定の公認会計士にアドバイスをください。
二代目・三代目として家業に戻った方の話を聞いていると、やはり何かしらの苦労はしているようです。ただ家業を継ぐという意味でどんな苦労をしているかは、本当に事務所によりけりですね。親や既存の職員さんとの関係性がうまくいかない、監査法人とのギャップ、都会とのギャップなど。
でもコミュニケーションの重要性と、偉そうにしないということは共通しています。

また家族との関係性や状況にもよると思いますが、自分だけの経験値を得ておくことも大切です。税務だけを学んでいては視野が狭くなってしまいますからね。遠回りに思えても、他の分野を経験したほうがいいと感じています。
会計士だと30歳ごろからマネージャーになる方が出てきますが、地方の税理士で30歳だとどういった会に行ってもほぼ最年少ですので、年齢を理由に焦る必要はないかもしれません。
例えば国際系の仕事をしていたら家業でも輸出入があるような会社の税務を担当できるようになるかもしれませんし、IPO業務を経験していたらスタートアップの案件が来る可能性もあります。時間が許すかぎり色々な経験を積んで、家業に戻るのがいいのではないでしょうか。
そういう意味では、私は監査法人時代は地銀の監査をして、J-TAPでも中小企業の再生計画に携わったことで、中小企業に関連する経験は積んできたものの、「幅」という視点では狭いような気もしています。
同時に、自分の価値の出し方には気を付けなくてはなりません。
例えば、多くの会計士は業務上Excelをよく触ってきているのでExcel操作は得意分野かと思います。当初は自分にしかできないことをやらないといけないと思っていたので、私もExcelを駆使した資料を作成していました。
しかし、一般的な職員さんはそこまでExcelを使いこなせないはずです。となると新たに作ったExcel業務は、私にしかできない仕事になってしまいます。事務所運営において、人に依存した業務があることは長い目で見ると良いことではありません。
それで今はむしろ、私にしかできない作業を減らす方向に動き、私の業務経験を事務所全体としてどうお客様に提供していくことができるかを考えています。
「後継ぎ」となると、すぐに価値を出したいと思うのはわかりますが、急ぎすぎると後からそれが却って邪魔になってしまう可能性があります。しばらくは様子を見て、事務所の雰囲気を見極めながら、ゆっくり価値を発揮していくのが良いのではないでしょうか。
── 河北さん、本日はありがとうございました。